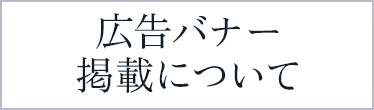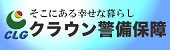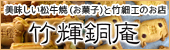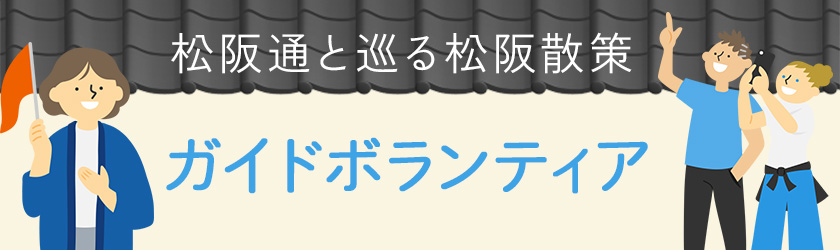2024年島田びわ販売について※予約受付終了しました。
2024年島田びわの販売は予約受付終了しました。
2024年島田びわの販売は予約受付となっています。
予約方法などについては下記の通りです。
<購入方法>
電話で予約注文⇒後日受取日の連絡がある⇒直売所「兄弟市」で受け渡し。
<受け渡し場所>
県道白山小津線沿いの「兄弟市(おとといいち)」
(近隣の施設:西日本セブンスリーゴルフクラブ)
<ご予約・お問合せ先 >
「松阪まち歩きデジタルスタンプラリー」 2024年4月25日~2025年2月28日
「松阪まち歩きデジタルスタンプラリー」を開催します。
期間:2024年4月25日~2025年2月28日
松阪をまち歩きしながら、スタンプラリーを楽しもう!
松阪市内7スポットに設置されたQRコードを読み取ってスタンプをGET!
スタンプ7個すべて集めたら豪華プレゼントの抽選に参加できます。
主催:豪商のまち松阪観光交流センター
問合せ:059
第18回 松阪撫子どんな花?祭り 令和6年5月25日(土)~31日(金)
第18回 松阪撫子どんな花?祭り
令和6年5月25日(土)~31日(金)
松阪撫子は松阪三珍花のひとつ。松阪撫子を市内で鑑賞することができます。
撫子献花式など行われます。
豪商ポケットパークでは、松阪撫子展が行われます。
日程や、内容について詳しくはチラシでご確認ください。
場所:松阪市中心市街地
お問合せ先:0598-21-0138 (ミズ・ネットワー
令和6年4月28日(日) 伊勢山上飯福田寺 戸開け式(春季大会式)
●日時 令和6年4月28日(日) 午前10時~式開始
詳しくは、チラシ又はPDFをご覧ください。
●場所 伊勢山上飯福田寺(松阪市飯福田町273)
●お問い合わせ
飯福田寺 TEL:0598-35-0004
伊勢山上飯福田寺 戸開け式(春季大会式)チラシ【PDF】
松阪沿岸の【潮干狩り全面禁止について】のお知らせ。
松阪漁業協同組合より【潮干狩り全面禁止について】お知らせです。
松阪沿岸のアサリ等貝類について、漁協を中心とした資源回復への取組を行っていますが、
漁獲に結びつかない厳しい状況が続いています。
日曜劇場『下剋上球児』松阪市内ロケ地巡り
⚾はじめに⚾
2023年10月よりTBS系にて日曜劇場『下剋上球児』が放送中!
日曜劇場『下剋上球児』のロケ地に「松阪」で撮影した場所があります。
ストーリーが進むにつれ、親しみがある場所が登場するかもしれません。日曜劇場『下剋上球児』を観てみましょう!
⚾三重県観光連盟さんの「観光三重」でドラマのことが紹介されています。※「ト
松阪フォトコンテスト2023 松阪の写真作品大募集 8月1日(火)~12月3日(日)
松阪フォトコンテスト2023 松阪の写真作品大募集 8月1日(火)~12月3日(日)
「いいなぁ、行ってみたい!」と思ってしまう、そんな魅力あふれる画像をお送りください。
松阪の風景や街並み、特産品や料理等の写真、街の笑顔など、 松阪を広く発信するため、
あなたが撮った、とっておきの瞬間を応募してみませんか?
入賞作品は松阪市観光協会のガイドマップや行事のポスター等で利用させていただく
七夕まつり☆鈴の音市 令和6年8月3日(土) START 夕方5:00~(夜)9:30まで
☆みんなで楽しむ 松阪の楽市楽座☆
七夕まつり☆鈴の音市
〇日時〇 2024年8月3日(土)午後5時~午後9時30分(小雨決行)
〇交通規制〇 午後5時~午後9時30分(予定)
〇場所〇松阪市中心市街地(本町~平生町)
〇内容〇飲食物の販売、ゲーム、野外演奏など。
お問い合わせ/ 松阪商工会議所 振興課 TEL
マンスリーベルファーム 2024年8月号
松阪農業公園ベルファーム情報
マンスリーベルファーム 2024年8月号
PDFこちらから
●お問合せ●
松阪農業公園ベルファーム
〒515-0845 三重県松阪市伊勢寺町551-3
TEL:0598-63-0050 (水曜休園)
松阪農業公園ベルファームHPはこちらから
●アクセス●
🚘お車をご利用の場合
伊勢自動車道
令和6年8月9日(金)岡寺山継松寺 四萬六千日
「四萬六千日」とは、観世音菩薩の功徳日のことです。
この日に参拝すると、四萬六千日参拝したのと同じご利益があると云われています。
「四萬六千日参り」ともいわれ、東京浅草・浅草寺の〈あさがお市〉〈ほうずき市〉が有名です。
松阪では、岡寺山継松寺で例年8月9日に行われ、一晩中、翌早朝まで参拝いただけます。
境内等の灯りでお参りの皆様をお迎え致しますので、是非夕涼みにおでかけくだ
【公募】市内観光事業者インバウンド対応支援補助金事業のご案内
この度、松阪市におけるインバウンド誘客を推進することを目的とした、
市内観光事業者インバウンド対応支援補助金事業のご案内させて頂きます。
以下、補助金事業の概要となります。
下記にございます補助金交付要綱をご一読頂き、
申請は、FAX、郵送、又はメールにてお願い申し上げます。
1.事業目的
松阪市内の観光事業者が外国人観光客に対応するために必要な設備の新設や改修など(以下「
題名の無い絵画展 2024 2024年7月26日〔金〕- 10月27日〔日〕
題名の無い絵画展 2024
2024年7月26日〔金〕- 10月27日〔日〕
開館日:金、土、日および祝日
開館時間:10:00-17:00
詳しくはコチラ➡サイトウミュージアム
題名の無い絵画展2024 表
題名の無い絵画展2024 裏
令和6年7月27日(土) 第27回嬉野おおきん祭り
◆令和6年7月27日(土) 16:30~ ※雨天順延
今年のテーマは「ありがとう~未来につなぐ感謝の想い~」
お御輿や屋台、ステージ発表などのイベントが楽しめ、フィナーレには花火が
上がります!「おおきん(ありがとう意)」をテーマにした嬉野地区最大のお祭りです。
開催場所/MEGAドン・キホーテUNY嬉野店 北側駐車場(嬉野中川新
8月25日(日)”10名限定”『カヤック体験と蓮ダム見学』 ~松阪市観光協会主催~
対象年齢【小学生~80歳まで】 ◆◆◆申込期限:8月11日(日) 16:00まで◆◆◆
★初心者でも安心 蓮ダムにてカヤック体験
★午後は、ダムのことを学ぶ「ダム見学室」や、
ダムの一番上から下まで約70mをエレベータで降りて、
ダム本体内部のトンネル体験などのダム見学
お問合せは、松阪駅観光情報センターへ
TEL:0598-23-7771 FAX:0598-26-4778
【松浦武四郎記念館】展示替えによる臨時休館について
松浦武四郎記念館は下記の期間、展示替えによる臨時休館となります。
観光でお越しいただく際は、ご注意ください。
臨時休館:令和6年7月23日(火)~令和6年7月25日3日間
※松浦武四郎誕生地は同期間中、通常通り開館します。
令和6年7月26日㈮から令和6年9月29日(日)まで、企画展「武四郎の晩年」を開催いたしますので、どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
詳しくはコ
松浦武四郎inウポポイ2024 2024年7月27日(土)・28日(日)
松浦武四郎inウポポイ2024
「北海道の名付け親」とされる松浦武四郎のふるさと三重県松阪市と、武四郎と交流のあった加賀伝蔵の
ふるさと北海道別海町との共催で「松浦武四郎inウポポイ2024」を開催します。
期 間 2024年7月27日(土)・28日(日)
会 場 エントランス棟
参加費 無料
詳しくはコチラ➡松浦武四郎inウポポイ2024 – ウポポイ(民族共生
夏休みに文化施設へ行こう!松阪キッズスタンプラリー
☆夏休みに文化施設へ行こう!松阪キッズスタンプラリー☆
松阪市公式のスマートフォン向けアプリ「松阪ナビ」を使って、小学生以下のお子さんを対象にデジタルスタンプラリーを実施します。
【松阪市文化財センター】と【下記対象施設のうち1か所】に入館して、アプリ内でスタンプを2つ集めた方全員に参加賞をプレゼント!
また、抽選でさらにスペシャルな景品も当たるチャンスです。
先着200名様で、参